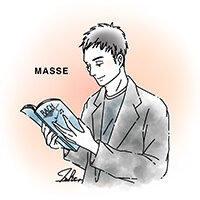※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
シリーズ《オーケストラ入門》、今回はクリスマスに舞台を持つ、チャイコフスキーのバレエ音楽『くるみ割り人形』を特集します。
『白鳥の湖』、『眠れる森の美女』と並んで、チャイコフスキーの「3大バレエ」と呼ばれる傑作です。
目次(押すとジャンプします)
「くるみ割り人形」をじっくり解説
「くるみ割り人形」はどうして短いのか
ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(Pyotr Ilyich Tchaikov1840-1893)が書いた最後のバレエ音楽、それが『くるみ割り人形』です。
このバレエは、全曲を演奏してもおよそ90分ほど。
これはバレエ音楽としてはかなり短い方。
たとえば、同じチャイコフスキーの作品でも『眠れる森の美女』などは2時間半以上かかります。
なぜ『くるみ割り人形』がそんなに短いかというと、これが書かれた当時、オペラとバレエをセットにして一夜で上演することが、フランスを起点に流行していた影響です。
つまり、一晩でオペラとバレエを上演するために、それぞれの時間が短くなったわけです。
チャイコフスキーへも、ロシアの劇場からオペラとバレエのセット注文が来ました。
そうして書かれたのが、バレエ音楽『くるみ割り人形』と歌劇『イオランタ』ということになります。
どちらも90分ほどの長さにおさえられています。
結果的には、そうした時間的制約があったことで、かえって、チャイコフスキーの創作の最後期にあたるこのバレエ音楽には、彼の音の世界が凝縮されることとなり、とてもまとまりの良い、類まれなバレエ音楽へと結実しました。
ちなみに、題材として『イオランタ』を選んだのがチャイコフスキー。
『くるみ割り人形』を題材に選んだのは劇場側だそうです。
チャイコフスキーは当初『くるみ割り人形』がバレエ向きの題材に思えなくて、作曲に乗り気ではなかったという意外な話も残っています。
パリでのエピソード
この歌劇『イオランタ』とバレエ『くるみ割り人形』の2曲の作曲を依頼されたころ、チャイコフスキー(1840-93)は50歳。
すでにいろいろな作品で国際的な名声を得ていた彼は、当時、ただでさえ多忙を極めていました。
このバレエ音楽の依頼を受けた1890年の翌年になって、実際に作曲を開始しますが、とにかく多忙なチャイコフスキー。
5月には、あのアメリカのカーネギーホールのこけら落とし公演を依頼されてアメリカを訪れたりと、当時、まさに世界を股にかけた忙しさで活躍をしていました。
そのなかで、音楽的に幸運な出会いがフランスで起こります。
チャイコフスキーは、フランスのパリで“ チェレスタ ”という新しい楽器と出会います。
これはその5年ほど前に発明されたばかりの、ほんとうに当時の最先端の楽器でした。
今では有名なこの楽器も、当時はそれほど有名ではなく、少なくともロシアにはまだ知れ渡っていない楽器でした。
そのキラキラした響きが、チャイコフスキーに作曲中の『くるみ割り人形』への新しいインスピレーションを与えたのは間違いがないようで、彼はすぐにこの楽器を注文しています。
そして、実際、チェレスタは“ 金平糖の踊り ”を中心に、第2幕で大活躍することになります。
この楽器との出会いにチャイコフスキーはよほど興奮していたようで、注文のときに「リムスキー=コルサコフやグラズノフに見つからないように」運んでほしいと指示しているくらいです。
管弦楽法の大家であるリムスキー=コルサコフなどに先に使われてしまうのを嫌がったんでしょう。
チャイコフスキーの人間ぽさが垣間見れるエピソードです。

あらすじ
物語は、クリスマス・イブに主人公のクララという女の子が、ドロッセルマイヤーというちょっと風変わりなおじさんから「くるみ割り人形」をプレゼントされたことから始まります。
この「くるみ割り人形」はすぐに、いたずらっ子の兄弟フリッツにこわされてしまうのですが、そこは、ドロッセルマイヤーおじさんに頼んで修理をしてもらいます。
やがて真夜中になって、「くるみ割り人形」の様子が気になったクララ。
「くるみ割り人形」が置かれている、クリスマスツリーのある大広間へひとりで入って行くと、突然、クララの体が小さくなり、さらには、目の前でねずみの王さま率いるねずみの大群と、くるみ割り人形率いる兵隊の人形たちの戦争が始まってしまいます。
くるみ割り人形が劣勢で窮地にたったとき、とっさにクララがスリッパを投げると、見事、ねずみの王さまに命中。
ねずみの大群は退散し、あの「くるみ割り人形」は王子様の姿に変身します。
そして、王子様は自分の命を救ってくれたクララのことを、自分が治めるお菓子の国へと招待します。
ここまでが第1幕。
第2幕は、そのお菓子の国でのさまざまな歓迎の様子が描かれます。
こうした非常にシンプルなストーリーですが、では、「お菓子の国へ行ったクララは最後は現実世界へ帰ってくるのか?」「すべて夢だったのか?」などなど、細かな点での台本のあいまいさは初演時から指摘されています。
そのあいまいさを逆手にとって、現在も、演出家によっては随分ちがう物語として演出されたりしています。

原作者ホフマンのこと
この物語の原作の作者は、E・T・A・ホフマン(1776-1822)というドイツの文人です。
彼の名前を省略せずに書くとエルンスト・テオドール・アマデウス・ホフマン。
「アマデウス」にピンと来た方は、クラシック音楽が好きな方です。
モーツァルトの本名がウォルフガング・「アマデウス」・モーツァルト。
実は、ホフマンはモーツァルトが大好きで、それで自身のペンネームに「アマデウス」を入れてしまったんだそうです。
エルンスト・テオドール・「ウィルヘルム」・ホフマン、というのが彼の本名でした。
そんな彼が書いた『クルミわりとネズミの王さま』という作品が、このバレエの原作です。
ホフマンはドイツの幻想文学の代表的人物で、その『クルミわりとネズミの王さま』も、原作のほうはバレエの台本ほど単純ではなくて、ミステリアスで、不可思議な物語になっています。
決して長い作品ではないので、このバレエが好きなかたには一読をお薦めしたい幻想小説です。
私が読んだのは岩波少年文庫のもので、現在も簡単に入手できます。
物語の展開は、大きくいえば同じ流れですが、バレエの台本よりも現実世界とファンタジーの世界の境界線があいまいで、そこが何とも言えない魅力を放っています。
『クルミわりとネズミの王さま』
(岩波少年文庫版)
ホフマンは多芸な人物で、自身でも作曲をするほどだったそうですが、クラシック音楽とはいろいろと縁の深い人物。
バレエ音楽の原作としてはこのチャイコフスキー:『くるみ割り人形』のほかに、ドリーブのバレエ音楽『コッペリア』もそうですし、オペラではオッフェンバックに歌劇『ホフマン物語』があります。
それから、シューマンが書いた『クライスレリアーナ』というピアノ曲も、ホフマンの作品からインスピレーションを受けたものです。

「くるみ割り人形」組曲と抜粋と全曲
🔰初めての『くるみ割り人形』は組曲で
この『くるみ割り人形』が演奏される場合には3つのパターンがあって、ひとつはバレエ音楽まるまる全体、それから作曲者自身の選曲による「組曲」、そして、その間をいく「抜粋版」です。
いちばんコンパクトな「組曲」は、有名な“ 花のワルツ ”をおしまいに持っている全8曲の構成。
これは、このバレエ音楽を作曲しているときに新作の依頼があって、けれど、それ用に別の音楽を作曲する時間がなかったチャイコフスキーが、作曲途中の『くるみ割り人形』から8曲を選んで、演奏会用の「組曲」としてまとめたものです。
“ 小さな序曲 ”にはじまって、おしまいの“花のワルツ”まで性格的な舞曲が並びます。
以前別の記事でご紹介しましたが、この曲はディズニー映画『ファンタジア』で、素晴らしいアニメーションをともなって、名指揮者ストコフスキーによる優れた演奏が刻まれています。
古い映画ですが、この曲が好きな方にお薦めの映像作品です。
🔰「組曲」の次に聴きたい①
『くるみ割り人形』には、組曲に含まれていない魅力的な曲が、まだまだたくさんあります。
とくに有名なのが“パ・ド・ドゥ( Pas de Deux )”。
これはドーシラソファーミレドと、ただ下がってくるだけの音階でメロディーを構成した、チャイコフスキーの旋律の天才を示す一曲です。
チャイコフスキーは『弦楽セレナード』でも同様の作曲技法を展開しています。
♪この曲だけまず聴いてみたいという方へ
ロシアの巨匠エフゲニー・スヴェトラーノフが指揮したフィンランド放送交響楽団の『ロシアのアダージョ』というオムニバス・アルバムに素晴らしい録音があります。
( Apple Music↑・ Amazon Music ・ Spotify などで聴けます)
🔰「組曲」の次に聴きたい②
それから、“ 雪のワルツ( Waltz of Snowflakes ) ”。
これは、第1幕のフィナーレとなる音楽。
舞台裏から児童合唱まで入ってくるという、斬新で、幻想的な音楽です。
♪この曲だけまず聴いてみたいという方へ
アンタル・ドラティ指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団の全曲版から。
( Apple Music ↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
「組曲」の次に聴きたい③
そして、この曲のフィナーレ、“ 終幕のワルツとアポテオーズ(Final Waltz and Apotheosis) ”へと進んでみてください。
♪この曲だけまず聴いてみたいという方へ
フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団の素晴らしいクライマックスを。
( Apple Music↑↓・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
たいていの「抜粋版」には、これら3曲が入っていることが多いです。
というわけで「組曲」に親しんだら、次はこうした「抜粋版」へ進みましょう!
ただ、「抜粋版」というのはチャイコフスキー自身が選曲したものはありません。
それぞれの指揮者が、それぞれ独自に選曲します。
そうして「抜粋版」を好きになったら、あとは自然に、全曲を聴かずにはいられなくなります!

わたしのお気に入り名盤
「くるみ割り人形」組曲
※リンク先は英語表記が多いので、チャイコフスキー『くるみ割り人形』→Tchaikovsky : Nutcracker というものを見つけて聴いてください。
《ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィルハーモニー》
私が最初に聴いたクラシック音楽の1つ。
“花のワルツ”が流れてきて「あ!これが花のワルツなんだ!!」と知ったときの嬉しい驚きは、今も忘れられません。
色々な演奏をその後聴くようになっても、やっぱり素敵な、思い出の演奏。
( YouTube↓・Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《ハンス・クナッパーツブッシュ指揮ベルリン・フィルハーモニー》
この曲は、意外な大指揮者がすごい演奏を残していたりするレパートリーのひとつです。
ドイツの大巨匠クナッパーツブッシュによる、1950年のベルリン・フィルとの演奏は、スケールがとんでもなく大きい、どこまでも自由な芸術。
古い録音で抵抗があるかもしれませんが、是非“ 花のワルツ ”だけでも試しに聴いてみてください。
まさに達人の音楽。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《セルジュ・チェリビダッケ指揮スイス・イタリア語放送管弦楽団》
幻の巨匠といわれたセルジュ・チェリビダッケが指揮したライブ録音。
“アラビアの踊り”の異様な精妙さ。
“花のワルツ”での後半、何かにとりつかれたかのように切迫していく音楽。
一度聴いたら忘れられない、心に刺さる演奏です。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
チェリビダッケは音楽を人生と同じく一回性のものと考えて、繰り返し聴く「録音」というものを否定していた指揮者だったので、正式なスタジオ録音がほぼありません。
そんな彼が若い頃に正式に残した録音のひとつが、ロンドン・フィルとの『くるみ割り人形』。
言い方を変えれば、これらを機に録音に見切りをつけたようです。
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
ちなみに、チェリビダッケは、後年になって、もう一度だけ正式にスタジオで録音したことがありました。
それは「秘密の小箱」という、自分が作曲した作品でした。
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
これは「ユニセフ国連児童基金」のためのものだったようで、そうした場面では、強い信念をしっかりと曲げられたところにも、この指揮者の大きさ、心根の真面目さ、優しさを感じます。
《アルトゥーロ・トスカニーニ指揮NBC交響楽団》
ちょっと面白い演奏として、イタリアの古き巨匠トスカニーニの演奏を。
アルトゥーロ・トスカニーニ(Arturo Toscanini, 1867-1957)にとっては、チャイコフスキー(1840-1893)は同時代人に近い存在。
演奏はすべての曲が凛として素晴らしいですが、特に“ 花のワルツ ”をお楽しみに。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《マルタ・アルゲリッチ&ニコラス・エコノムによる2台ピアノ版》
変わったところで、2台ピアノで組曲を演奏したものがあります。
しかも、名ピアニスト2人による素晴らしい演奏で、このバージョンの代表盤となっている有名なもの。
編曲は第2ピアノを担当している、キプロス出身のエコノムによるもの。
わたしは、ノスタルジックな響きで彩られたこの“ 花のワルツ ”が好きで、たまにどうしても聴きたくなります。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
「くるみ割り人形」抜粋版
《エフレム・クルツ指揮フィルハーモニア管弦楽団》
エフレム・クルツ(1900-1995)は、ロシア生まれ。
イザドラ・ダンカンやアンナ・パブロワといった伝説的なダンサーたちと関りが深かったため、バレエ音楽に造詣が深く、バレエ音楽のスペシャリストという印象の人です。
『くるみ割り人形』でも非常に素晴らしい演奏を繰り広げています。
YouTubeとその他の配信とでは曲目が違っていますので、是非、それぞれを聴いてみてください。
( YouTube / Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団》
ストイックな音楽づくりをする、ハンガリーの巨匠フリッツ・ライナー(1888-1963)が手兵のシカゴ交響楽団とレコーディングしたもの。
まさに“硬派”なチャイコフスキー。
その鉄壁のアンサンブルが、鋭く、でも、ロマンティックに音楽を彩っていく光景は圧倒的。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《エフゲニー・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル》
ロシア随一の巨匠エフゲニー・ムラヴィンスキー(Evgeny Mravinsky、1903-1988)は、『くるみ割り人形』でいかにもこの指揮者らしい独自の選曲を演奏しています。
“花のワルツ”など有名曲はほぼカット(!)。
第1幕のくるみ割り人形とねずみたちの戦闘の前あたりから終幕までと、第2幕の“パ・ド・ドゥ”、おしまいのワルツとアポテオーズが選ばれていて、ちょうど上で「組曲の次に聴きたいもの」としてご紹介した場面あたりだけでまとめています。
でも、その辛口な姿勢の裏側で、実はとってもロマンティックな、熱い音楽をしていることが魅力。
“パ・ド・ドゥ”を聴いていただくと、それがはっきりとわかると思います。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
「くるみ割り人形」全曲版
《アンタル・ドラティ指揮アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団》
私が初めて全曲を聴いたのがこの演奏。
そして、結局、今もこれがいちばん好きです。
ハンガリー出身の名匠アンタル・ドラティ(1906-1988)には、たまに「おやっ?」と思うレコーディングがあったりしますが、これは最上のものです。
コンセルトヘボウの豊かな響き、音によるドラマを壮麗に展開しています。
これより前にロンドン交響楽団と録音したものも素晴らしくて、より明解なスタンスでの演奏。
ただ、そちらは“ 雪のワルツ ”の合唱が児童合唱ではなく、女性合唱。
私は音程がはずれようと児童合唱での演奏のほうが好きなので、やはりコンセルトヘボウの録音を聴きたくなることが多いです。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《シャルル・デュトワ指揮モントリオール交響楽団》
フランス音楽で一時代を築いたコンビによる演奏。
とっても丁寧な音づくりがここでもなされています。
色彩的で、さっぱりとした、でも、味わいもある素敵な録音。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
《エルネスト・アンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団》
聴けば聴くほど味わい深いのが、この演奏。
アンセルメ(1883-1969)は、もとはスイスのローザンヌ大学で数学の教授をしていたという人。
26歳のころに決心をして指揮者に転向。
大作曲家ストラヴィンスキーの諸作品やファリャのバレエ音楽『三角帽子』の世界初演をしたり、20世紀のバレエ音楽にも大きな関りをもった巨匠です。
演奏しているスイス・ロマンド管弦楽団というのは、彼が創設したオーケストラ。
この『くるみ割り人形』は、色彩的なのに落ち着いたたたずまいがあって、古典的な表情を持っているのに、よく聴くと20世紀の響きがして、このコンビでしか実現できないような高尚な音楽をしています。
この曲を聴き込んだ人の方が楽しめる演奏かもしれません。
アンセルメが日本に来て、京都の詩仙堂を訪れた際の写真をどこかで見たことがあるんですが、まさにあの写真に写っていたアンセルメの姿を思い出します。
ぱっと見たところは、古いお寺にたたずむ穏やかな老紳士。
でも、そこに写っている、あの深い表情と、眼光の鋭さ。
紛れもない、20世紀の巨人。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)

♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
オンライン配信の聴き方については、「クラシック音楽をオンライン(サブスク定額制)で楽しむ~音楽好きが実際に使ってみました~」のページでご紹介しています。
♪お薦めのクラシックコンサートを「コンサートに行こう!お薦め演奏会」のページでご紹介しています。
判断基準はあくまで主観。これまでに実際に聴いた体験などを参考に選んでいます。
♪実際に聴きに行ったコンサートのなかから、特に印象深かったものについては、「コンサートレビュー♫私の音楽日記」でレビューをつづっています。コンサート選びの参考になればうれしいです。
♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグをTシャツトリニティというサイト(クリックでリンク先へ飛べます)で販売中です。