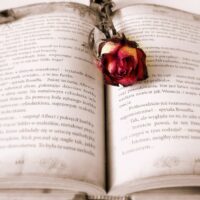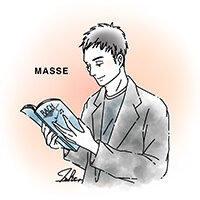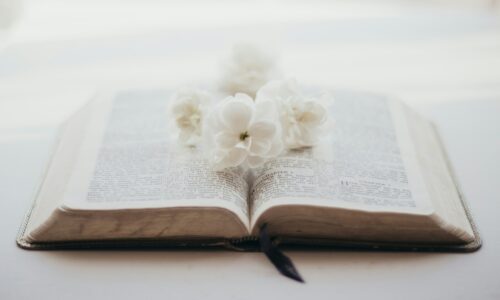※当サイトはアフィリエイトを利用しています
目次(押すとジャンプします)
ベルリン・フィルの野外コンサート
森のなかでのピクニック・コンサート
ヴァルトビューネ・コンサートは、ドイツの名門ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が夏休みにあわせて、森のなかで行う野外コンサート。
夕暮れ時から夜にかけて、映像で見ていても実に美しい光景がひろがる、素敵なコンサートです。
今回は、私がこのコンサート・シリーズでとくに好きな回を、5つだけ選んでご紹介したいと思います。
映像は現在すべてベルリン・フィルが管理していて、ベルリン・フィル・デジタル・コンサート・ホールというサイトで見ることができます。
また、現在多くが廃盤ですが、以前発売されていたDVDを中古で手に入れる手段もありますので、そちらの情報もご紹介していきます。

特選①プレートル(指揮)フレンチ・ナイト
1992年ジョルジュ・プレートル(指揮)フランスの夜
当初、小澤征爾さんが指揮する予定だったと聞いていますが、代役でフランスの名指揮者ジョルジュ・プレートル(Georges Prêtre, 1924 – 2017)が出演しました。
そして、これが場外ホームランのような名舞台となりました。
ヴァルトビューネ・コンサートでいちばん素晴らしいものをひとつ選べと言われたら、私は間違いなくこれをお薦めします!
何といっても、プレートルの全盛期の指揮姿が見れるのが楽しい。
そう、「楽しい」という言葉がぴったりの指揮ぶりです。
表情が俳優のようにゆたかで、手の動き、体の動きもとってもユーモラス。
唯一無二といっていい体の使い方をしていて、その点で、彼は生まれながらの指揮者だったと言えるでしょう。
前半のプログラム
冒頭の『ローマの謝肉祭』から猛烈にオーケストラをあおっていて、果敢な指揮ぶりを見せます。
2曲目は、名ピアニストのレオン・フライシャー(Leon Fleisher, 1928 – 2020)をソリストに、ラヴェルの『左手のためのピアノ協奏曲』が演奏されます。
当時、フライシャーは右手を病いで使えなくなり、左手のピアニストとして活躍していました。
実は、このコンサートから何年もたってからですが、彼の病いの治療法が確立されて、晩年は、両手のピアニストとして復帰しました。
そのときに“ Two Hands ”という、文字通りのアルバムを残しています。
後半はさらに名演奏の連続
日が暮れかかった後半のプログラムは、ドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』で始まります。
ベルリン・フィルの名手カール・ハインツ・ツェラーがまだ在籍していて、とっても素晴らしいソロを聴かせています。
森がだんだんと夜になっていく光景をうつくしく捉えたカメラ映像も出色です。
そこに次の曲目、『カルメン』組曲の華々しい演奏がすごい勢いで打ち上げられます。
「間奏曲」の美しさといい、「ジプシーの踊り」のニュアンスの豊かさと迫力の凄まじさといい、何か音楽の女神が降り立っているかのような、もしくはバッカスの神々がやってきたかのような、明らかに何かが舞い降りたような特別な演奏を聴くことができます。
「ボレロ」の熱演
『カルメン』の熱狂の後、ざわめきがおさまらない会場のなかに静かに小太鼓のリズムが始まります。
メイン・プログラムのラヴェル作曲『ボレロ』の始まりです。
私は子どもの頃、この演奏で初めて『ボレロ』を聴きました。
一緒に観ていた父親に「ほら、いつの間にか音が大きくなっているだろう」と言われて初めて、曲がいつの間にかクレッシェンドしていることに気づきました。
各楽器のソロがうつくしくて、その音色や歌心の豊かさに耳を奪われているあいだに、どんどん楽器編成が拡大していたわけです。
後半になると指揮しているプレートルの顔も真っ赤になってきて、力こぶを入れて全身で指揮をしています。
YouTube動画で観られる「ホフマンの舟歌」
アンコールに答えて、まずはオッフェンバック『ホフマンの舟歌』が演奏されます。
当日ワールドカップが行われていたらしく、ラジオ片手に聴いていた聴衆の一部がドイツのゴールに熱狂し、曲が終わるちょっと前にフライングのような拍手が沸き起こっています。
まさにその『ホフマンの舟歌』の動画が公式に出ていましたので、是非ご覧ください。
このあと、さらにアンコールでシュトラウスの『ラデツキー行進曲』。
はじまった瞬間にお客さんが「待ってました!」という大喝采。
そして、それも終わると、真のアンコール曲、リンケ作曲『ベルリンの風』。
これはお客さんも口笛や拍手で参加する、会場が完全にひとつになれる音楽。
プレートルは最後まで絶好調で、この熱狂の主役を務めています。
彼は後年、ウィーン・フィルのニューイヤーコンサートに出演したりして評判をとりましたが、本当の意味で彼の絶頂期を見られるのは、このコンサート映像です!
この時期にもっとたくさんの映像が残されていたらよかったのにと、今も思います。
DVD情報
「フレンチ・ナイト」のタイトルで、これまでに2回ほど発売されました。
そこまでレア商品ではないので、在庫があるときは普通にあります。
およそ2000円~3000円が相場のように思います。
特選②小澤征爾(指揮)ロシアン・ナイト
1993年小澤征爾(指揮)ロシアの夜
ついに1993年、小澤征爾さんが指揮台に立ちました。
小澤征爾さんはたくさんの映像商品がありますが、私がいちばん手放せないのはこれです!
前半のプログラム
1曲目はリムスキー・コルサコフの序曲『ロシアの復活祭』という、なかなか渋い選曲ではじまります。
小澤征爾さんはウィーン・フィルとこの曲を録音していたので、お気に入りの一曲だったのかもしれません。
2曲目にはチャイコフスキーの『くるみ割り人形』組曲が選ばれていて、どちらもすばらしい演奏で言うことなしです。
3曲目にボロディンの「ダッタン人の踊り」。
当時オーケストラの顔といっていい活躍をみせていた首席オーボエ奏者シェレンベルガーの素晴らしいソロが聴かれます。
特に見どころは後半
何といっても、この小澤征爾さんの回の見どころは後半。
日暮れどきの会場に強烈な一撃がさく裂してはじまるストラヴィンスキーのバレエ組曲『火の鳥』(抜粋)からです。
組曲の前半をとばして、いちばん激しい“カスチェイの魔の踊り”から急に始まります。
野外なので、弱音の多い前半をカットしたのかもしれません。
その強烈なリズムと色彩で、会場はあっという間に飲み込まれます。
一世一代の「1812年」
そして、その興奮さめやらぬなか、メインの曲目であるチャイコフスキーの序曲『1812年』がチェロの合奏で始まります。
これは、小澤征爾さんの面目躍如たるというか、一世一代の名演奏になったといってもいいくらい、最初から最後まで美しさと緊張感であふれた名演奏になっています。
ラストの大砲の箇所は、よく実際に大砲を鳴らしたりしている演奏がありますが、ベルリン・フィルは普通に「大太鼓」などの打楽器でそれらを超えてきます。
それも、大砲で聴くよりも迫力を感じるくらいの凄いフォルテ。
曲がおわったとたん、凄まじい歓声がわきおこります。
これを会場で聴いた人は本当に幸運な人たちです。
YouTube動画で観られる「剣の舞」
アンコールはハチャトゥリアン『剣の舞』にはじまります。
この動画が公式でありましたのでご覧ください。
アンコールはさらに、チャイコフスキーの『弦楽セレナード』の“ワルツ”へと続きます。
聴衆のだれかの口笛があまりに上手に入って、会場に笑いが起きています。
そして、前年と同じく『ラデツキー行進曲』に『ベルリンの風』。
もう会場はロックコンサートのようなお祭り騒ぎになってきます。
小澤征爾さん、一世一代の名舞台が、ここに記録されています。
DVD情報
『ロシアン・ナイト』のタイトルで発売されました。
以前は中古が¥3000前後で販売されていましたが、相場がすこし上がっているようです。
③クラウディオ・アッバード(指揮)イタリアン・ナイト
1996年クラウディオ・アッバード(指揮)イタリアの夜
当時の音楽監督クラウディオ・アッバード( Claudio Abbado, 1933-2014)が、たった1回だけ登場した貴重な回。
オペラ座で最高のキャリアをつみかさねた、さすがアッバードといった構成で、アンジェラ・ゲオルギューやブリン・ターフェルといった当時第一線の人気オペラ歌手が登場して、ヴェルディやベルリーニ、ロッシーニのオペラからの聴きどころが盛りだくさんでした。
このときは、日本時間で早朝4時か5時くらいからNHKで生放送され、早起きして見ました。
イタリア・オペラの世界
冒頭がヴェルディの歌劇『ナブッコ』序曲で、アッバードの爽やかな情熱ですっかり目がさめたのを覚えています。
この日もワールドカップのドイツ戦とかさなって、ところどころ、ラジオ片手に聴いているお客さんの歓声が突然入ります。
アバドも最初は驚いていますが、「よかったね!」とグッドサインを送ったりしています。
ソプラノのアンジェラ・ゲオルギューはベルリーニの『カプレーティ家とモンテッキ家』から「婚礼の衣装を着せられ〜ああ、いくたびか」を歌います。
これは本当にうつくしい歌。
あのワーグナーが嫉妬したという音楽。
このとき初めてこのアリアを聴きましたが、一度聴いただけで忘れらないほどの美しさ。
ホルンのソロを伝説のホルン奏者ゲルト・ザイフェルトが吹いています。
YouTube動画で観られる「ウィリアムテル」
ザイフェルト以外にも、音楽監督アッバードが指揮するということで、こちらも伝説のクラリネット奏者のカール・ライスターも参加していますし、コンサート・マスターも2名座っています。
YouTubeには公式動画として、ロッシーニの有名な『ウィリアム・テル』序曲の一部が公開されていますが、今では伝説になっている奏者が多数参加しているのを観ることができます。
こうして、このコンサートではロッシーニやヴェルディの有名な序曲も演奏されているのですが、どちらかというと、歌が入っている曲の方に重点がある印象で、歌が入ってくる曲はすべてがすべて素晴らしいです。
オーケストラだけで演奏しているものでは、アンコールに演奏されるロッシーニの『セビリアの理髪師』序曲がお薦めで、これはアッバードにしかできないような、颯爽として色彩的なすばらしい演奏です。
恒例のアンコール『ベルリンの風』ですが、このときはアッバードだけの特別バージョンになっていて、この日に演奏されたオペラの名旋律がコラージュ風にちりばめられたものになっています。
そして、何といってもテンポがとても速い。
切れ味鋭いリズムが刻まれ、引き締まった行進曲が会場にさく裂します。
この『ベルリンの風』だけでも、やはりアッバードという指揮者は、なにか他の指揮者と一線を画すものがあると伝わってきます。
DVD情報
「イタリアン・ナイト」という名前で発売されました。
相場は¥2000前後だと思います。
④ズービン・メータ(指揮)ホワイト・ナイト
1997年ズービン・メータ(指揮)サンクトペテルブルクの夜
小澤征爾さんもロシア音楽でしたが、インド出身の名指揮者ズービン・メータもロシア・プログラム。
前半では指揮者としても活躍しているダニエル・バレンボイムがピアノ・ソロでチャイコフスキーのピアノ協奏曲に登場しています。
でも、お薦めは、後半のロシアのオーケストラ作品の数々です。
後半のプログラムがお薦め
ムソルグスキーの小品、それから、よく超絶技巧のソロを聴かせるために演奏される『くまばちの飛行』など、楽しい音楽が次々に演奏されます。
メインはリムスキー・コルサコフの『スペイン奇想曲』。
これはさすがベルリン・フィルというダイナミックな演奏で、音楽がよく歌っていて、とってもロマンティックな味わいもある、できそうでできない素晴らしい演奏です。
そして、アンコールで最初に演奏されるチャイコフスキーの『白鳥の湖』~“ワルツ”。
これもスペイン奇想曲とならんで、この日の特にすばらしい演奏のひとつです。
YouTube動画で観られる「タイボルトの死」
公式動画にはそのあとに演奏されたプロコフィエフのバレエ『ロメオとジュリエット』~“タイボルトの死”が公開されています。
このあとに、恒例の『ベルリンの風』が演奏されたのですが、上機嫌の指揮者メータは指揮棒をバトンのようにくるくる回していて、曲の途中で指揮棒を落っことすというハプニングも映っています。
これには本人も照れ笑い、楽団員も思わず笑いながら弾いています。
DVD情報
「ホワイト・ナイト」のタイトルで発売されました。
相場は¥2000前後だと思います。
⑤マリス・ヤンソンス(指揮)アンコール・ナイト
2002年マリス・ヤンソンス(指揮)アンコール・ナイト
ラトビア出身の人気指揮者マリス・ヤンソンス(Mariss Jansons, 1943-2019)が、ヴァルトビューネ・コンサートに出演した2回目。
「アンコール・ナイト」のタイトルどおり、コンサートのアンコールとして演奏される短い曲をたくさん演奏してくれています。
途中、ロシアのヴァイオリニスト、ワディム・レーピンがゲストとして参加。
数曲演奏していますが、見どころはアンコールで演奏したパガニーニの『ベニスの謝肉祭』。
その超絶技巧とユーモラスな曲に聴衆が大喜び。
アンコールをもう一度アンコールする展開になって、たいへん盛り上がります。
アンコール曲がうまかったヤンソンス
ヤンソンスは数々のアンコール的小品を見事に指揮しています。
なかには日本の外山雄三さんの曲まで入っていて驚かされます。
私はヤンソンスの演奏会は何度か聴くことができましたが、いつもアンコールの演奏のうまさには聴き入りました。
彼の演奏でいちばん心に今も残っているのは、アメリカのピッツバーグ交響楽団の公演で、チャイコフスキーのバレエ音楽『眠りの森の美女』から“パ・ダクシオン”を演奏したときのこと。
あの日はブラームスの交響曲がメイン・プログラムだったんですが、それはたいして印象に残らないものでしたが、アンコールになった途端、めいっぱいオーケストラを鳴らして、弦も管も歌いに歌わせたチャイコフスキーがはじまって、圧巻の演奏でした。
こういう小品がとっても上手な指揮者だったわけです。
見どころは「ウィーンの市民」
この年のヴァルトビューネ・コンサートのいちばんの見どころは、何といってもツィラーのワルツ『ウィーンの市民』です!
会場の何万人という聴衆が右に左にワルツのリズムにあわせて体を揺らし、会場全体がワルツに揺れ動きます。
『ウィーンの市民』で踊るベルリン市民。
音楽でみんながひとつになっている感動的な光景。
演奏しているベルリン・フィルのメンバーもときおり客席を眺めながら演奏しています。
まさに理想的な音楽のあり方で、あの場に居合わせた人は、あの数分間を一生忘れないでしょう。
そして、このヴァルトビューネ・コンサート2002『アンコール・ナイト』についてはAppleMusic(リンクが貼ってあります)で動画配信がされています。
➡現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクになっています。
■Apple Music Classical日本版が解禁!クラシック音楽に特化~弱点もちょっとあります
■AppleMusicでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
彼はヴァルトビューネ・コンサートと同じ趣向の「アンコール・アルバム」をオスロ・フィルと録音していて、そちらもお薦めです。
ここでは演奏されていないヴィラ・ローボスのブラジル風バッハが私のお気に入りの演奏です。
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴くことができます )
YouTube動画で観られる「雷鳴と電光」
この年の映像は残念ながら公式YouTubeには公開されていないようなので、代わりにヤンソンスが初めて指揮した1994年のヴァルトビューネ・コンサートからヨハン・シュトラウスのポルカ『雷鳴と電光』をリンクしておきます。
DVD情報
ヴァルトビューネ2002『アンコール名曲の夕べ』というタイトルでDVDが発売されました。
相場は¥2000前後だと思います。

クラシック入門に最適な映像の数々
夏の風物詩、ベルリン・フィルのヴァルトビューネ・コンサート。
クラシック入門にも最適な、たのしいコンサートの数々です。
ポピュラーな曲目が多く、それでいて、オーケストラも指揮者も一流。
これ以上の音楽への入り口はないと言えるくらいです。
ぜひ、動画を見るなり、DVDを手に入れるなりして、ゆったりと楽しい音楽の時間を過ごしてみてください。
♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクになっています。
■Apple Music Classical日本版が解禁!クラシック音楽に特化~弱点もちょっとあります
■AppleMusicでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
Amazon Musicアマゾン・ミュージックも配信されている音源の量が多くお薦めできます。
■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
■オンライン配信の聴き方全般については、「クラシック音楽をオンライン(サブスク定額制)で楽しむ~音楽好きが実際に使ってみました~」のページでご紹介しています。
♪お薦めのクラシックコンサートを「コンサートに行こう!お薦め演奏会」のページでご紹介しています。
判断基準はあくまで主観。これまでに実際に聴いた体験などを参考に選んでいます。
♪実際に聴きに行ったコンサートのなかから、特に印象深かったものについては、「コンサートレビュー♫私の音楽日記」でレビューをつづっています。コンサート選びの参考になればうれしいです。
♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグをTシャツトリニティというサイト(クリックでリンク先へ飛べます)で販売中です。