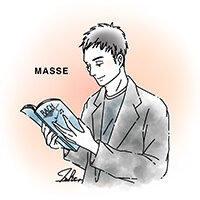※当サイトはアフィリエイトを利用しています
東京交響楽団の音楽監督としてのラストシーズンをむかえたジョナサン・ノット。
インタビューでの予告通り、そのシーズン開幕に、ブルックナーの交響曲第8番ハ短調を「初稿(第1稿)」で取りあげました。
ジョナサン・ノット(指揮)東京交響楽団
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調「第1稿」
第1稿
「演奏不可能」。
ブルックナー(Anton Bruckner, 1824-1896)から送られてきた新作「交響曲第8番」のスコアをみたヘルマン・レーヴィ(Hermann Levi, 1839-1900)は、この新作を「演奏不可能」と、そう結論づけたそうです。
「芸術上の父」とまで心酔していたレーヴィからのまさかの反応に、ブルックナーはひどく狼狽し、伝記によっては自殺を考えたとまで書かれています。
ブルックナーは、結果的に「改訂」の筆をとることになるわけですが、この一連のエピソードに触れるたび、私は、レーヴィをはじめとするブルックナーの同時代人たちが、いかにブルックナーの音楽を受け止めきれていなかったか、結局、ブルックナーの天才が理解されるには20世紀を待たなければいけなかったのだと、そんな風に感じていました。
けれども、今回、こうしてジョナサン・ノットと東京交響楽団の非常に優れた演奏で、しかも、録音ではなく“ 実演 ”でもって「第1稿」に接してみると、ヘルマン・レーヴィという指揮者の見識は、実はたいへんなものだったのではないか、そんなふうに思えてきました。
考えてみれば、あのワーグナーがパルジファルの初演を託したほどの指揮者なわけですから、当然と言えば当然なのですが。
「第1稿」をインスピレーションの原初の姿、そのもっとも純粋な発露として、最上位に置く考えもあります。
でも、私自身は、今回、初めて実演で初稿を聴いて、これまで録音などで聴いていたとき以上に、「第1稿」に困惑させられました。
来たるべきものが、まだヴェールの向こうに隠れている。
ブルックナーが何かを探し求めて、たしかにそれに触れているけれども、まだ掴みきれてはいないような、そんなもどかしさを随所に感じました。
もちろん、それは私が改訂後の、通常演奏されるノヴァーク版やハース版の凝縮された姿を知ってしまっているせいかもしれませんが、ヘルマン・レーヴィは初稿を見た段階で、そうしたものを感じ取っていたのかもしれません。
ブルックナーに率直に「演奏不可能」と伝えたのは、音楽的な良心にしたがった、実に優れた進言だったのではないかと思えてきます。
改訂と創造
しかし、何より圧倒されるのは、それに応えたブルックナーの改訂の凄さです。
第2稿を知る耳で聴くと、第1稿は、意外なくらい普通の展開があったり、いっぽうで、あまりに複雑で、もってまわったように感じられる展開もあります。
私には音楽がどこに向かっているのかわかりにくく感じられるところも多く、そうしたものを耳にしていると、天才ブルックナーといえども、最初から頂上にいるわけではないのだと思ってみたりもしました。
それゆえ、いっそう、そこから成し遂げられた改訂の作業に“ 凄み ”を感じてしまいます。
これに似たことは、以前、ブラームスの交響曲第1番の第2楽章のカールスルーエ版を聴いたときにも感じました。
大作曲家たちの“ 改訂の力 ”には、作曲そのものと寸分違わない、突き抜けた創造性を感じさせられます。
未聴の方はぜひ、ブラームスの交響曲第1番の第2楽章のカールスルーエ版を聴いてみてください。
その後の改訂がいかに正しく、まさに「あるべきところにあるべきものが響く」とはどういうことなのかを教えられます。
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
ブルックナーにもどると、改訂作業によって作品は短くなったので、当然、第1稿でしか聴くことのできない、ここでしか触れられない美しさというのもあります。
例えば、第3楽章で聴かれるフルートとハープによる楽節などは、実演で聴くと、その美しさはほんとうに格別です。
ですが、そうした美しい楽節すらも、ブルックナーは書き換えたり、あるいは、削除していった。
ブルックナーの研ぎ澄まされた、厳しい審美眼。
第1稿を聴きながら、その先にやがて訪れる改訂作業の重みを感じさせられます。

ノットの批評的「第1稿」
そんな「第1稿」をジョナサン・ノットはどう演奏したのか。
第1稿をとりあげる指揮者たちの多くは、ノヴァーク版やらハース版といった通常の版をさけることで、いわゆる“ ブルックナー指揮者たち ”が築き上げたブルックナー演奏史から解放され、彼らの自由を謳歌するように見受けられます。
けれども、今回のノットはどうも違っていました。
おそらく、ジョナサン・ノットは、今後、この第1稿をとりあげることは、あまりないんじゃないかと思います。
私が聴きながら感じていた、ある種のもどかしさのようなものを、ステージ上のノットもまた感じているような、そんな演奏に聴こえたからです。
その意味で、この演奏は、創造的な“ 批判精神 ”をもった演奏になっていたと思います。
第1稿を支持する多くの指揮者たちは、確信犯的に“ ブルックナーらしさ ”を避けますが、ノットはとても“ ブルックナーらしい ”様式によって指揮をしていました。
それゆえに、往年のブルックナー指揮者たちが抱いたであろう「第1稿」の違和感は、ありのままに描きだされました。
それでいて、冒頭からおしまいまで、全楽章、いっさい弛緩することがない。
首尾一貫した緊張感でつらぬかれた演奏には、もう脱帽するしかありませんでした。
貴重なブルックナー体験
ノットのブルックナーがいつもこうだったわけではありません。
「第9番」を取りあげたときには、過度にアグレッシブで、無理に新しくあろうとする姿勢に閉口させられました。
あのコンサート、前半で演奏されたマーラーの第10番アダージョは、対照的に素晴らしかったですが。
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
それが、何年か前の「第2番」では、古典的な均整をともなった、充実のブルックナーに昇華されていて、心打たれました。
「第2番」はノットの得意曲なのか、ラジオで聴いたスイス・ロマンド管弦楽団との演奏も堂々たるものでした。
♪オンライン配信は未配信(2025年4月現在)
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
➡ジョナサン・ノット&東京交響楽団の美しいブルックナー第2番、ウェーベルン、シェーンベルクを聴いて
そして、今回の「第8番」は「第2番」に続く素晴らしい出来栄えでした。
このコンビは10年ほど前に「第8番」をすでに取り上げていて、そちらは「ノヴァーク版第2稿」という標準的な版を選択していました。
これはこのコンビの初レコーディングだったそうです。
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
今回の公演で、もし以前と同様に通常の版が選択されていたら、まったく段違いの感銘を受けただろうと容易に想像できます。
ほんとうはそれが聴きたかった。
あれこれ考えず、ただただ、ノットと東京交響楽団のブルックナーに包まれていたかった。
それが正直な感想ではあります。
ただ、それでも、ほんとうにこれは貴重な機会。
得がたいブルックナー体験のひとつとなったのは間違いありません。
オーケストラは、1年ほど前に聴かれた不調が嘘のよう。
管、弦、打、いずれもが充実していました。
ノットの音楽監督としてのラストシーズンは、素晴らしい幕開けとなりました。
東京交響楽団とジョナサン・ノットは、今、のちのち語り草になるであろう、美しい夕映えの輝きのなかにあります。

♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクです。
➡【2025年】クラシック音楽サブスクはApple Music Classicalがいちばんお薦め
Amazon Musicアマゾン・ミュージックも配信されている音源の量が多く、お薦めできます。
■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
♪お薦めのクラシックコンサート
➡「コンサートに行こう!お薦め演奏会」
♪実際に聴きに行ったコンサートの感想・レビュー
➡「コンサートレビュー♫私の音楽日記」
♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグを制作&販売中
➡Tシャツトリニティというサイトで公開中(クリックでリンク先へ飛べます)