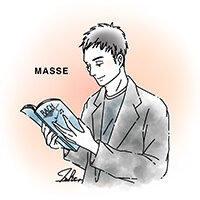※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
シリーズ《オーケストラ入門》。
今回は、クラシック音楽のファンにとって、元旦恒例の「ウィーン・フィルのニューイヤーコンサート」がテーマです。
今回は、私がとくに好きなニューイヤーコンサートのライブ録音を7つ厳選してご紹介していきます。
目次(押すとジャンプします)
わたしの好きなニューイヤーコンサート7選
1987年:ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)
ニューイヤーコンサートの大きな転換点となった、楽壇の帝王ヘルベルト・フォン・カラヤン(Herbert von Karajan, 1908-1989)が登場したコンサート。
カラヤンがステージに姿をみせた途端に会場が総立ちになり、スタンディングオベーションでその登場が迎えられたそうです。
実際、演奏はとても素晴らしいもので、普段とはまったく違う、特別な一夜になっています。
華やかで、飛んだり跳ねたりするようなシュトラウスの世界ではなくて、ノスタルジックなウィーンの落陽を見るような、ひとつの時代の終わりを感じさせる響きが胸に残ります。
指揮者に手厳しい発言が多いウィーン・フィルの名コンサートマスター、ライナー・キュッヒル氏は、どこかのインタビューで、カラヤンが指揮したときのポルカのテンポを絶賛していました。
速くもなく遅くもない、絶妙なテンポが設定されています。
このときは、喜歌劇『ジプシー男爵』序曲、喜歌劇『こうもり』序曲などなど、有名曲がたくさん選ばれていて、どの曲も聴きどころです。
『春の声』では、ソプラノ歌手のキャスリーン・バトルが出演しています。
♪わたしのお気に入り
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
私がこの年の曲目でいちばん好きなのは、ヨーゼフ・シュトラウスのワルツ『 天体の音楽』(“ Sphärenklänge ”)です。
繊細な音の重なり、どこか寂寥感すら漂う、ノスタルジックで陰影にとむ音楽が紡がれています。
最晩年のカラヤンの音楽づくりは、若いころとはちがった、心の奥にまでしみ込んでくる響きを持っています。
この曲を指揮しているときの、カラヤンの青く澄んだまなざしが忘れられません。
CDを買おうという方には、上にリンクしてある1990年頃発売の古いものや、それ以前に出たものをお薦めします。
中古で数百円で手に入り、現在出ているものより、音が良いです。
ライブの映像は、数年前、ようやくBlu-ray版が出ました。
1994年:ロリン・マゼール(指揮)
私がいちばん取り出して聴く頻度が高いのは、この1994年のものです。
指揮がロリン・マゼール(Lorin Maazel, 1930-2014)。
ニューイヤーコンサートのCDを試しに1枚買ってみようという場合は、この1994年のアルバムをいちばんにお薦めします。
上の画像はAmazon商品ページにリンクしてありますが、そのほか「 4988009949321 」の商品番号で検索してみてください。
マゼールはもっと若いころにたくさんこのコンサートを指揮していましたが、1990年代以降も何度か登場しました。
特にお薦めなのが1994年と1996年の2回です。
ですが、この2回にかぎって、どういうわけか映像商品が出ませんでした。
私が大好きだったマゼールの、ほんとうに良い指揮ぶりが見れた回だったので、いつか映像が出ることをずっと楽しみにしています。
こういう演奏をびわ湖ホールのコンサートでも聴かせてほしかった。
わたしのお気に入り
このときの選曲はおどろくべき素晴らしさ。
有名曲と聴いたことがないけれど素敵な曲のバランスがとってもよかった年です。
こうしたバランスは、このコンサートをたくさん指揮したマゼールならではの選曲眼ということになるでしょう。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
このアルバムは、聴きはじめると自然と最後まで聴かずにいられないアルバム。
なので、一曲を取り出すのがほんとうに難しいのですが、会場のいい雰囲気がいちばんはっきりと伝わるということで、ヨーゼフ・シュトラウスのポルカ『憂いもなく』(“Ohne Sorgen”)を上げておきます。
途中から鉄琴、グロッケンシュピールが鳴り響きますが、これは指揮台でマゼールが叩いています。
1989 & 1992年:カルロス・クライバー(指揮)
伝説の指揮者カルロス・クライバー(Carlos Kleiber、1930-2004)。
年に1回指揮台に立つか立たないかというほどで、後年になるほど演奏会の数が激減した指揮者でした。
たいへんな完璧主義者で、キャンセルも多かった彼が、この華やかな舞台に登場するとあって、大きな話題となり、実際、伝説的な公演になりました。
私がTVで初めて目にしたニューイヤーコンサートは1992年、偶然にも、カルロス・クライバー登場の回でした。
すっかりと魅了された私は、すぐに大きなCD屋さんへ彼の録音を探しに行きました。
ですが、どんなに探しても、そこで売っていたのは『運命』のCD1枚だけ。
彼がその完璧主義ゆえに指揮する回数も少なく、録音も非常に限られた数しかない天才指揮者だなんて全く知らなかった私は、「きっとクライバーという指揮者はまだまだ有名じゃなくて、これから出世していくんだな」と、しばらく勘違いしていました。
わたしのお気に入り
彼は1989年と1992年の2回、ニューイヤーコンサートに登場しました。
1989年の初登場のときは選曲がとても渋いもので、そのなかでは、ヨハン・シュトラウスⅡ世の喜歌劇『こうもり』序曲(“ Die Fledermaus ” )が有名曲で親しみやすいです。
クライバーらしい、快速の、空を舞うような演奏が展開されています。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
いっぽうで1992年の2回目の登場では、『トリッチ・トラッチ・ポルカ』や『雷鳴と電光』など、人気曲がたくさん選ばれました。
『雷鳴と電光』(“ Unter Donner Und Blitz”)では、最後の音がまだ鳴っているなかで会場から拍手がわき起こります。
そのほか、ヨハン・シュトラウスⅡ世のワルツ『千一夜物語』(“ Tausend und eine Nacht ”)が夢見るような美しい演奏になっています。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
彼の演奏は、特に映像でみたいところです。
その華麗な指揮ぶりは、まさに“ 天才 ”と呼ぶにふさわしいものです。
1993 & 1997年:リッカルド・ムーティ(指揮)
リッカルド・ムーティは1993年に初登場。
颯爽たる、たいへん素晴らしい演奏を披露しました。
そして、その次の登場となったが1997年。
こちらも出色の、勢いにあふれたコンサートでした。
ムーティのシュトラウスは、基本的にテンポがどれも速めです。
第2部の冒頭にはスッペの喜歌劇『軽騎兵』序曲( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)のたいへんな名演奏が聴かれます。
当時、テレビの生中継を観ていましたが、第2部の1曲目にもかかわらず、会場はたいへんな盛り上がりを見せました。
わたしのお気に入り
この年のいちばんのお薦めは、ヨーゼフ・シュトラウスのワルツ『ディナミーデン』(“ Dynamiden ”)。
このときのテレビ中継では、この『ディナミーデン』にバレエの映像がつけられていて、シンデレラをモチーフにした実に見事な物語が重ねられていました。
ニューイヤーコンサートのバレエ映像のなかで、私にとっていちばん印象的なのがこのときのものです。
演奏も出色のものです。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
『ディナミーデン』は、あとにリヒャルト・シュトラウスが楽劇『ばらの騎士』で引用したことでも名高いワルツ。
私は、ムーティはヨーゼフ・シュトラウスの大家だと思っています。
とても詩的で繊細な、抒情的音楽が引きだされます。
彼は1993年登場の際、ヨーゼフ・シュトラウス:『トランスアクツィオン』でも、心に迫る、美しい名演奏を披露していました。
2015年:ズービン・メータ(指揮)
インド出身のズービン・メータは、アジア人として初めてこのコンサートの指揮台に立った人で、1990年の登場以降、常連の指揮者のひとりです。
ウィーンで若いころに勉強をしていたということもあって、とっても良いシュトラウスを聴かせてくれる指揮者のひとりです。
いちばん最近の登場はこの2015年のもの。
2000年代に行われたニューイヤー・コンサートのなかでは、2021年のリッカルド・ムーティの回と並んで、特に出色のコンサートでした。
わたしのお気に入り
ヨハン・シュトラウスⅡ世の人気作のひとつにワルツ『酒、女、歌』(“ Wein, Weib und Gesang ”)というのがあります。
同時代の大作曲家で親友だったブラームスが好きだった一曲でもあるこのワルツ、実はとっても長い前奏がついています。
あまりに長いので、たいていカットされるのですが、この2015年の公演で、メータはカットなしで演奏しました。
普段は聴けない序奏部をまるまる聴ける、とても貴重で、とても素敵な演奏。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
1979 & 1974年:ウィリー・ボスコフスキー(指揮)
ウィーン・フィルの名コンサートマスターでもあったウィリー・ボスコフスキー(Willi Boskovsky,1909-1991)が指揮していた時代、1974年の貴重な映像がDVDで出ています。
まだ、このコンサートがそこまで国際化していない時期のものです。
今となっては、ニューイヤーコンサートの原点のひとつといえる時代の記録です。
それだけに、聴衆もオーケストラも、どこか普段着の良さがあります。
和気あいあいとした会場の雰囲気が素敵な時代です。
わたしのお気に入り
ボスコフスキーが指揮した最後の回、1979年のニューイヤーコンサートは、オンライン配信でも聴くことができます。
( Apple Music↑・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
このころの雰囲気を感じられる曲目として、ヨハン・シュトラウスⅡ世のポルカ『狩り』を挙げておきます。
アンコールとして2回演奏されますが、鉄砲が響くたびに、会場から普段着の笑い声がもれてきて、とても素敵な雰囲気を味わえます。
演奏も今よりもぐっとローカルな色の、土地のワインのような素朴な香りがします。
2021年:リッカルド・ムーティ(指揮)
ニューイヤーコンサート史上初の無観客のなかで行われた、2021年のニューイヤーコンサートです。
コロナ禍によるロックダウン下のウィーンで行われた公演。
このコンビの演奏は2021年の11月に行われた日本公演で実演で体験しましたが、今、いちばんウィーン・フィルがその本領を発揮できるのは、このリッカルド・ムーティ指揮のときだと確信しています。
1990年代にはその颯爽とした、速めのテンポで駆け抜けるようなシュトラウスを演奏していたムーティ。
そのあまりの速さに、ウィーン・フィルの名コンサートマスター、ライナー・キュッヒル氏が「自分は二度とイタリア人の指揮でシュトラウスを演奏したくない」とインタビューで話していたほどです。
キュッヒル氏とちがって、私はテンポの速い、若々しいシュトラウス演奏も大好きですが、こうして老成したムーティが聴かせる、落ち着いたシュトラウスもまた、たいへんに素晴らしいものになっています。
わたしのお気に入り
( Apple Music↓・Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
ここでは、このコンサートの定番であるヨハン・シュトラウスⅡ世のワルツ『美しく青きドナウ』(“ An der schönen blauen Donau ”)をあげておきます。
このアルバムには、スッペの『詩人と農夫』序曲やコムザークの『バーデン娘』など、ほかにも聴きどころがたくさんありますが、ムーティが行った英語のスピーチ(トラック17)もしっかりと収録されています。
今までのニューイヤーコンサートでは、あまりスピーチをしなかったイメージのムーティが、とても長いメッセージを世界へ向けて送っています。
「音楽は娯楽ではありません。私たちがここにいるのは職業だからではないのです、使命だからです」という真摯な訴えかけには、素直に感動させられました。
この年は、前述のとおり、ロックダウン中のウィーンで行われたために、無観客での開催ということで、そこへの違和感を感じた人もたくさんいらしたようです。
わたしはむしろそうした中でも演奏会を止めなかったこと、そして、そこから響いてきた音楽、それから、リッカルド・ムーティの言葉に、大きく勇気づけられた一夜でした。
こちらは2022年1月現在、まだまだ簡単にBlu-rayが入手できます。

♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
オンライン配信の聴き方については、「クラシック音楽をオンライン(サブスク定額制)で楽しむ~音楽好きが実際に使ってみました~」のページでご紹介しています。
■AppleMusicでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
♪お薦めのクラシックコンサートを「コンサートに行こう!お薦め演奏会」のページでご紹介しています。
判断基準はあくまで主観。これまでに実際に聴いた体験などを参考に選んでいます。
♪実際に聴きに行ったコンサートのなかから、特に印象深かったものについては、「コンサートレビュー♫私の音楽日記」でレビューをつづっています。コンサート選びの参考になればうれしいです。
♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグをTシャツトリニティというサイト(クリックでリンク先へ飛べます)で販売中です。