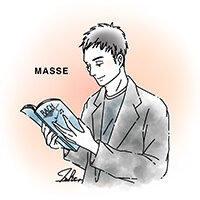※当サイトはアフィリエイトを利用しています
目次(押すとジャンプします)
リッカルド・ムーティ(指揮)東京春祭オーケストラ2025
“ 小品をならべたプログラムというのは、実は指揮するのがとても難しいものです。
次から次へと作品が移り変わっていく、その短い時間のなかで、それぞれの作品の世界を描き切らなければなりません。”
そんなことをずっと昔、ムーティがインタビューで話していました。
前半のプログラムを聴きながら、なるほど、まさにその通りなんだと、その言葉を思い出していました。
小品プログラムの難しさ
巨匠リッカルド・ムーティ(Riccardo Muti, 1941 ナポリ – )が83歳の高齢ながら、今年の春も上野にやってきてくれました。
プログラムは、前半にイタリア・オペラからのオーケストラ作品、後半はレスピーギの交響詩「ローマの松」をメインにすえたものでした。
2025年4月12日(土)
15:00@東京文化会館
ヴェルディ:歌劇《ナブッコ》序曲
マスカーニ:歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》間奏曲
レオンカヴァッロ:歌劇《道化師》間奏曲
ジョルダーノ:歌劇《フェドーラ》間奏曲
プッチーニ:歌劇《マノン・レスコー》間奏曲
ヴェルディ:歌劇《運命の力》序曲
(休憩)
カタラーニ:コンテンプラツィオーネ
レスピーギ:交響詩《ローマの松》
前半プログラムの意外な出来栄え
「ナブッコ」序曲の冒頭を聴いた瞬間、「おや?」と思います。
響きがまばらで、フレージングもどこか中途半端でさだまらない。
ここ数年来のムーティのコンサートでは聴いたことがないような、言葉は悪いですが「生煮え」のような音楽が聴こえてきました。
それはトゥッティになっても同じで、意外なほどこちらに届いてこないフォルテが響きます。
もちろん、近年のムーティらしい、心のこもったカンタービレ、テヌートを基調としたフレージング、そして、日本を代表する若手奏者たちの耳をひく響きなど、聴きどころはあるにはあります。
けれども、「ナブッコ」に限らず、どの作品もいまひとつ生煮えで、冒頭のムーティの言葉のとおり、それぞれの世界が成立する前に曲が終わってしまい、次から次へと移っていってしまうという印象でした。
ムーティは決して小品プログラムが不得手な指揮者ではありません。
それどころか、彼ほどしっかりと小品をレパートリーに入れ続けている名指揮者は、現代では他にあまりいないくらいでしょう。
では、いったい何の歯車がうまくかみあっていないのか。
♪ムーティ&シカゴ交響楽団「イタリアン・アルバム」
「ナブッコ」序曲、「マノン・レスコー」間奏曲、「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲など、この日のプログラムのいくつかが収録されています。
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
「できあがったオーケストラ」
カラヤン(Herbert von Karajan, 1908-1989)が「良きにつけ悪しきにつけ、できあがってしまっているオーケストラのほうが指揮しやすいものです」と話していたことがありました。
この前半を聴いていて、その言葉もまた、思い出しました。
東京春祭オーケストラは常設のオーケストラではありませんから、オーケストラのなかに土台となる音楽ができあがっているわけではありません。
つまり、ムーティがこだわっている箇所であればあるほど、確信をもった響きがオケから聴こえてきますが、いっぽうで、ムーティがオケに任せてしまうと、表現やアンサンブルがどこか曖昧で、確信を欠いたものになる嫌いがありました。
こういう、非常設のオーケストラで小品をならべたプログラムをやるというのが、意外なほど難易度が高いものなのだというのは、今回、はっきりと教えられました。
それに、あくまで想像ですが、これら前半の曲目については、それほど綿密なリハーサルをしなかったのではないか、短時間のリハーサルで終えてしまったのではないかと、そんな印象を持ちました。
なので、率直に、前半の演奏内容には少しがっかりしました。
小品をならべたプログラムが難しいのであれば、当然、演奏時間が長いものほど安心できることになります。
前半の出来に意気消沈しながらも、わりと長い曲が置かれた後半のプログラムに期待して、休憩時間をすごしました。

カタラーニ:コンテンプラツィオーネ
後半1曲目はアルフレード・カタラーニ(Alfredo Catalani, 1854 – 1893)の「コンテンプラツィオーネ」。
10分を超える、抒情的作品。
あまり聴く機会のない作品ですが、ムーティはしばしば取り上げている作品です。
この作品になった途端、前半がうそのように、強く、強く耳をひく音楽が立ち上りました。
メンバーがまるっきり変わってしまったのかと思うくらい、実際そう思って、ステージ上を何となく見渡してしまったくらい、まったく“ 別物 ”の音楽が響いてきました。
前半の曲目にも、たとえば「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲に代表されるように、弦楽器が非常にうつくしい作品がありましたが、このカタラーニで聴かれた美しさは、その表現の確信の度合い、思い入れの度合いが段違いでした。
それはつまり、そのままムーティの思い入れのちがい、ということになるのでしょう。
郷愁をたたえた音楽は、弱音になればなるほど雄弁になっていきます。
特に後半、ソットヴォーチェでささやくように奏された弦楽の響き。
ちょっとやそっとでは忘れられないほど、強い音楽的印象を刻まれました。
♪カタラーニのコンテンプラツィオーネが収録されたスカラ・フィルとの録音
♪シカゴ交響楽団とのマスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」全曲版におさめられた“ 間奏曲 ”
これはさすがの演奏です。
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
レスピーギ:ローマの松
そして、レスピーギの交響詩「ローマの松」です。
この作品になると、冒頭からオーケストラの響きは完全に立ち上がり、まるでイタリアの太陽を思わせる、眩いほどの輝きと色彩が降り注いできました。
レスピーギのオーケストレーションの“ 色彩 ”を、ここまで鮮やかに、しかも、それをフランス系の指揮者ではなく、ムーティから聴くことになるとは思ってもいませんでした。
さらに第2部「カタコンバ付近の松」では、低弦が、近年のムーティらしい、和声的で、重く、ゆったりと沈み込むような響きで、作品の世界をいっそう深い方向へと押し広げます。
面白かったと言っていいのか、第3部「ジャニコロの松」では、ずいぶんたくさんの鳥の鳴き声が盛大に鳴り響いてきて、驚きました。
オーケストラの静かな抒情との“ アンバランス ”は珍しいくらいで、狙ったものなのか、失敗したのかはわかりませんでしたが、私は聴いていて、とっても楽しい心地にさせられました。
もともとはレコーディングされた鳥の声を流すのがスコアの指定だと思いますが、ムーティは水笛を複数使っていたように聴こえました。
そして、最後の第4部「アッピア街道の松」。
確固たる足どりと、まさにクライマックスにふさわしい、壮麗な響き。
そして何といっても、あの息の長いクレッシェンドの連続。
そのクレッシェンドの描き方がじつに見事で、それはやがて、バンダをふくめたオーケストラの圧倒的な輝きと力感に達しました。
もう何十年もまえ、ムーティとスカラ・フィルのコンサートで、レスピーギ「ローマの祭り」の圧倒的な実演を聴いて、結局、いまでもそれを超える、あるいは、それと並ぶ「祭り」を体験できずにいますが、この「ローマの松」もそうしたものになっていく気がします。
♪若き日のムーティ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団によるレスピーギ:ローマ三部作
( Apple Music ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
CDで聴く場合は、あまりリマスターされていない、1990年代はじめまでに出たものがお薦めです。
最近のものは、リイシュー&リマスターされすぎて、小奇麗な音に変わってしまっています。
9月に再来日!
前半の曲目にわくわくしてチケットを手にした公演でしたが、終わってみれば、後半のカタラーニとレスピーギに心打たれた公演になりました。
終わり良ければすべて良し。
これほどの後半を聴かされたら、ぐうの音も出ません。
ムーティ、今年はオペラはないのかと思っていたら、9月に再来日して、イタリア・オペラ・アカデミーを開催、ヴェルディ「シモン・ボッカネグラ」をとりあげることが発表されました。
公式:https://www.tokyo-harusai.com/academy_2025/
来日のころには84歳。
そんな高齢で年に二度来日してくださるのは、私にとって「僥倖」としか言いようのない、ほんとうに幸運なことです。
失礼な話ですが、ムーティがこれほど美しく歳を重ねていく音楽家だとは思ってもいませんでした。
今後も、その演奏を1回1回、大切に受け止めていきたいと思います。

♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクです。
➡【2025年】クラシック音楽サブスクはApple Music Classicalがいちばんお薦め
Amazon Musicアマゾン・ミュージックも配信されている音源の量が多く、お薦めできます。
■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
♪お薦めのクラシックコンサート
➡「コンサートに行こう!お薦め演奏会」
♪実際に聴きに行ったコンサートの感想・レビュー
➡「コンサートレビュー♫私の音楽日記」
♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグを制作&販売中
➡Tシャツトリニティというサイトで公開中(クリックでリンク先へ飛べます)