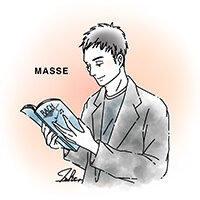※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています
「本格的なコンサートに行ってみたい!」
という方向けに、お薦めの“純”クラシック・コンサートをご紹介しています。
自分のコンサート体験・知識だけを基準にえらんでいます。
このページは随時更新。
どうぞ、ときおりご覧になってください。

こちらでは2025年の4月をご紹介。
そのほかの月は、『コンサートに行こう!お薦めの演奏会』ページから移動をおねがいします。
【日付順】おすすめクラシック・コンサート
さっそく、お薦めコンサートの一覧です!
■4/4(東京)
ルネ・ヤーコプス(指揮)ビー・ロック・オーケストラ「30年ぶりの来日」
古楽界の大物のひとり、ヤーコプスが30年ぶりの来日。
御年78歳、ということは、前回の来日時はまだ40代だったことになります。
とりあげられるのがヘンデルの「時と悟りの勝利」というオラトリオで、ほんとうに好きな人向け、玄人向けの公演かもしれませんが、注目の公演。
この東京オペラシティ以外の公演はないのでしょうか…?
■4/4~6(和歌山・島根・兵庫)
尾高忠明(指揮)大阪フィル「白鳥の湖」
4/4➡和歌山公演
4/5➡島根公演
4/6➡兵庫公演
大阪フィルの特別公演で、音楽監督の尾高忠明さんの指揮。
後半のチャイコフスキー:バレエ音楽「白鳥の湖」セレクションがお薦めポイント。
超有名曲ですが、これをレパートリーにいれている名指揮者は意外と少数。
N響でも取り上げられていた、尾高忠明さん自身のセレクションが披露されるのではないかと思います。
■4/4(群馬)
小林研一郎(指揮)群馬交響楽団「ベートーヴェン:交響曲全曲演奏会~第1番&第3番“ 英雄 ”」
群馬交響楽団の創立80周年記念、ベートーヴェンの交響曲全曲演奏会の第1回です。
毎回、指揮者が変わる趣向のようで、シリーズのなかで一番惹かれるのは、このコバケンさんが指揮する第1回。
熱量と実のある開幕になってほしいです。
■4/5・6(東京・神奈川)
ジョナサン・ノット(指揮)東京交響楽団「ブルックナー8番」
4/5(土)18:00
@サントリーホール
公式サイト:https://tokyosymphony.jp/concert/52716/
4/6(日)14:00
@ミューザ川崎
公式サイト:https://tokyosymphony.jp/concert/52956/
当ブログ一押しの指揮者ジョナサン・ノット&東京交響楽団の新シーズンにしてラスト・シーズンの開幕公演。
意外なことに、演目は再演で、すでにレコーディングも済んでいるブルックナー:交響曲第8番ハ短調。
このコンビの初レコーディングがこのアルバムだったので、もしかしたら、それを意識しての選曲かもしれません。
♪ブルックナー:交響曲第8番(ジョナサン・ノット&東京交響楽団、2016年7月16日サントリーホールLive録音)
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
2024年が生誕200年の記念年だったブルックナー(Anton Bruckner, 1824-1896)の交響曲第8番は、演奏時間が80分前後の大作。
大作曲家ブルックナーの代表作であると同時に、星の数ほどあるクラシック音楽の金字塔のひとつ。
ノット&東京交響楽団の黄金コンビが、そのラストシーズンをどうスタートさせるのか、大注目のコンサート。
■4/18(愛知)
舘野泉(piano)山下一史(指揮)愛知室内オーケストラ
舘野泉さんのために書かれた左手のためのピアノ協奏曲を、ベートーヴェンの交響曲第1番&第7番ではさむ、という興味深いプログラム。
躍進いちじるしい楽団の、躍動的な演奏が期待されます。
「進化と深化」と題された、愛知室内オーケストラのシーズン開幕公演。
■4/19(神奈川)
横山幸雄(ピアノ&指揮)日本フィル「オール・ショパン・プログラム」
日本を代表するピアニストのひとり、横山幸雄さんが日本フィルを弾き振りする注目公演。
前回にひきつづき今回もオール・ショパンのプログラムで、「ピアノ協奏曲第1番」がメインディッシュ。
ピアノが大好きなひと、ショパンが大好きな人におすすめの公演。
■4/19・20(北海道)
札幌交響楽団~エリアス・グランディ首席指揮者就任記念~「マーラー:復活」
札幌交響楽団のあたらしい首席指揮者、まだ40代の若きエリアス・グランディの就任披露公演。
こうした機会にふさわしい、マーラー:交響曲第2番「復活」という大曲がえらばれています。
こういう特別な機会には、特別な演奏がうまれやすいものなので、大いに期待したい公演。
■4/25(大阪)
山下一史(指揮)大阪交響楽団「モーツァルトのディヴェルティメントとセレナード」
意外なくらいオーケストラのコンサートで取り上げられる機会が減っているのが、モーツァルト作品。
古楽の隆盛以降、指揮者たちが以前のように気軽に取り上げることができなくなったのが、いちばんの要因だと思います。
山下一史さんは、きっと正攻法の、まっすぐなモーツァルトを聴かせてくれるはずです。
■4/26・27(東京)
広上淳一(指揮)日本フィル ヴェルディ:歌劇「仮面舞踏会」(セミステージ形式)
指揮者の広上淳一さんがスタートさせる新シリーズの第1弾。
古巣の日本フィルとともに、ヴェルディの歌劇「仮面舞踏会」をセミステージ形式で上演します。
セミステージということなので、演奏会形式ではなく、演技や演出もある程度入る上演になるはず。
リッカルド・ムーティやジョナサン・ノットのおかげで、すっかり日本でも人気となったコンサートホールでのオペラ上演。
あたらしい人気シリーズとなるか、注目の第1弾。
東京・春・音楽祭(4月公演)から
公式ホームページ:https://www.tokyo-harusai.com/
ここからは、上野を中心におこなわれる東京春音楽祭の4月公演からおすすめをピックアップ!
■オクサーナ・リーニフ(指揮)読売日本交響楽団 プッチーニ:歌劇「蝶々夫人」(演奏会形式)
4/10(木)15:00@東京文化会館大ホール
4/13(日)15:00@東京文化会館大ホール
読売日本交響楽団の演奏会形式オペラ、今回は“ ある晴れた日に ”のアリアでも人気のプッチーニ:歌劇「蝶々夫人」。
指揮は、ウクライナ出身の女性指揮者オクサーナ・リーニフ。
バイロイト音楽祭に登場した最初の女性指揮者として話題となった、躍進中の指揮者。
注目公演です。
■リッカルド・ムーティ指揮東京春祭オーケストラ「ローマの松」
4/11(金)19:00@東京文化会館大ホール
4/12(土)15:00@東京文化会館大ホール
現在のクラシック界の帝王リッカルド・ムーティ(Riccardo Muti, 1941 ナポリ – )が2025年も登場。
今年はオペラではないものの、やはり祖国イタリアの作曲家に焦点をあてたプログラム。
メインのレスピーギ「ローマの松」の前には、ヴェルディの「運命の力」や「ナブッコ」の序曲、「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲などなど、オペラの名曲がずらっと並んでいます。
これほどの指揮者が、こうした名曲ばかりをあつめたコンサートをひらく機会は非常に少なく、貴重。
プログラム的に、初心者でも安心のコンサート。
♪イタリア・オペラ名曲集
リッカルド・ムーティ(指揮)
シカゴ交響楽団
2017年LIVE録音
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
■ルドルフ・ブッフビンダー・ピアノ・リサイタル「シューベルト」
4/15(火)19:00@東京文化会館小ホール
ドイツ正統派のピアニスト、ブッフビンダーが今年も登場。
昨年好評だったベートーヴェンのあとは、シューベルト。
4つの即興曲D899と最後のピアノソナタ第21番変ロ長調D960が組まれています。
詩情あふれるシューベルトが聴けるのではないでしょうか。
ブッフビンダーには、このコンサートとまったく同じ組み合わせのレコーディングがあります。
2012年の録音。
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
ブッフビンダーはこのリサイタルのほかに、NHK交響楽団のメンバーと室内楽公演もあります。
4/18(金)19:00@東京文化会館小ホール「シューベルト:ピアノ三重奏曲第1番&第2番」
4/19(土)18:00@東京文化会館小ホール「シューベルト:ピアノ五重奏曲《ます》ほか」
■ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団J・シュトラウス:喜歌劇「こうもり」演奏会形式
4/18(金)15:00@東京文化会館大ホール
4/20(日)15:00@東京文化会館大ホール
今回いちばん驚いたラインナップ。
東京春祭にジョナサン・ノット&東京交響楽団のコンビが登場です。
しかも、演奏会形式でシュトラウスの「こうもり」とは二度びっくり!
音楽のよろこびが目いっぱい詰まった喜歌劇です。
2025-26シーズンで東響を退任するジョナサン・ノット。
特別な1年を見事に彩る名舞台を期待したい公演です。
♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクです。
➡【2024年】クラシック音楽サブスクはApple Music Classicalがいちばんお薦め
Amazon Musicアマゾン・ミュージックも配信されている音源の量が多く、お薦めできます。
■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
お願い
こちらのページはあくまで大まかな地図としてお役立ていただいて、詳細は各公式サイト・プレイガイドで必ず確認をお願いします。
個人で集めている情報ですので、記載ミスなどもあるかもしれません。
その際にはどうぞご容赦ください。

初心者向け:コンサートの選び方
曲目より、演奏者で選ぶ
■初めてコンサートに行くとなると『モルダウ』や『運命』といった聴いたことがある曲目で選びたくなりますが、そうではなくて、まずは誰が演奏するのかで選びましょう。
わかりやすく例えると、美味しいものが食べたければ、メニューより前に、美味しいお店を探すことが大切なのと同じです。
■とはいっても、初心者であればあるほど、演奏者や指揮者の名前なんて知らないと思います。
そこで、このブログでは、クラシック音楽が大好きな私が、あくまで主観的に、自分でもチケットを買いたいと思う、お薦めのコンサート情報を厳選して掲載していきます。
場所もクラシック・コンサートが集中する東京、関東、首都圏にこだわらず、北海道、東北、中部、近畿、関西、四国、中国、九州、沖縄まで、自分がそこに住んでいたら「行ってみたい!」と思う、とにかく気になるものを素直にピックアップしています。
判断基準は、あくまでも、自分がこれまで実際に聴いたときの体験などの「主観」。
その分、しがらみや忖度はありません。
クラシックをふだん聴かない方は名前も知らない演奏家が並んでいるかもしれませんが、「クラシック音楽と向き合ってみたい!」という方に、多少なり参考になったらうれしいです。
高いチケットは買わないで
とくに重要なことは、
- いきなり高いチケットを買わない
- 当日券ではなく、前売りで買う
の2点です。
■クラシック・コンサート初心者がいきなり高い席を買うのはお薦めしません。
理由は簡単で、クラシックのコンサートはハズレが多いからです。
「高いお金を出したのにハズレだった」としたら、二度と行きたくならないのが人情。
ですので、初めのうちほど、まずは手ごろな価格でチケットを手に入れてましょう。
具体的には、オーケストラ公演であれば、はじめのうちはP席(オーケストラの裏側)がお薦めです。
■また、「前売り」については、一般的には、だいたい3~6か月前くらいにチケットの発売が開始されます。
半年先というとずいぶん先に思えるかもしれませんが、人気の公演はそれでも完売してしまいますし、最後に残るのはたいてい高い席です。
■こうした話を、「コンサートの選び方&チケットの買い方【初めてのクラシック・コンサート】」というページにまとめています。
■さらには、チケットを手に入れたあと初心者の方が気になるであろう、「クラシックコンサートに行くときの服装」のことなどは、「コンサート当日の不安を解消!服は何を着る?持ち物は?【初めてのクラシック・コンサート】」というページにまとめています。

♪このブログではオンライン配信の音源も積極的にご紹介しています。
現状、Apple Music アップル・ミュージックがいちばんおすすめのサブスクです。
➡【2024年】クラシック音楽サブスクはApple Music Classicalがいちばんお薦め
Amazon Musicアマゾン・ミュージックも配信されている音源の量が多く、お薦めできます。
■Amazonでクラシック音楽のサブスクを~スマホは音の図書館
♪お薦めのクラシックコンサート
➡「コンサートに行こう!お薦め演奏会」
♪実際に聴きに行ったコンサートの感想・レビュー
➡「コンサートレビュー♫私の音楽日記」
♪クラシック音楽にまつわるTシャツ&トートバッグを制作&販売中
➡Tシャツトリニティというサイトで公開中(クリックでリンク先へ飛べます)