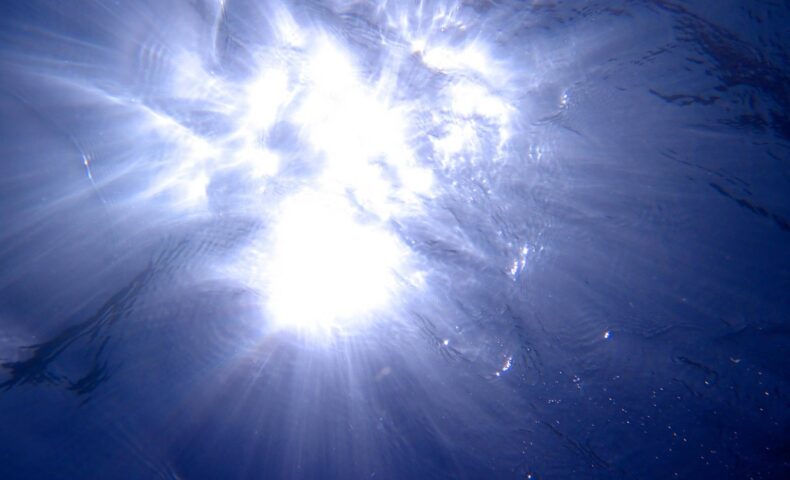2022年5月29日(日)14時から、埼玉県の所沢市にある所沢ミューズで、アリス=紗良・オットのピアノ・リサイタル『エコーズ・オブ・ライフ』を聴いてきました。
ここでは、そのリサイタルを聴きながら考えていたこと、それから10年ほど前、初めて彼女のリサイタルを聴いたときのことを綴ってみたいと思います。
目次(押すとジャンプします)
行く予定ではなかったリサイタル
もともと、私はこのリサイタルに行く予定はなかったのですが、クラシック音楽情報誌『ぶらあぼ』を眺めていたら、彼女のインタビューが載っていて、そこで初めて彼女が大きな病気と闘っていることを知りました。
どういう病気かは具体的な記述がなかったので、そのあと検索してみたところ、彼女がいう「病気」というのは、多発性硬化症でした。
音楽ファンはどうしたって、あのイギリスの名チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-1987)の悲劇を連想せずにはいられない病名で、すっかり驚いてしまいました。
今回の演奏会のチラシにもそうした類いのことは全く書かれていませんでしたし、検索したことで以前メディア等で話題になっていたのを知りましたが、寡聞にして、そうした事情はあのインタビュー記事を読むまで私は知りませんでした。
コンサート会場で配られたアリス=紗良・オット自身の言葉よるパンフレットには、現在は治療が功を奏していて症状が出ていないことなどが書かれていましたし、実際、演奏そのものも自由闊達でしたが、いずれにしても、現在の医学では完治ができない難病であるのは事実で、ほんとうに言葉もありません。
映像つきコンサート
このリサイタルにもともと行く予定がなかったと書きましたが、それは、このリサイタルが「映像つき」であるのが理由でした。
映像つきのコンサートというのは近年わりと多い類のものですが、今までの経験上、そうしたコンサートに行ってあまり満足したことがないので、私の個人ブログの「お薦めのコンサート」のページでも紹介するのは断念していました。
今回それでも聴きに行ったのは、私はアリス=紗良・オットのピアノがもともと好きで、あのインタビュー記事を読み、もし病気の進行のせいで彼女のピアノが聴けなくなったらという焦燥感に襲われてしまったからです。
ただ、そうして聴きに行ってみて、やはり映像付きのコンサートというものは難しいと感じながら帰路につくことになりました。
演奏中、いったい何が違和感なんだろうとずっと考えていました。
まずは、そのことから、書いていきたいと思います。

映像と音楽のこと
暗転したホールでは、アリス=紗良・オットのピアノ付近が薄明りになっていて、その向こう側に大きなスクリーンが設置され、映像が映し出されました。
演奏されたのは、ショパンの『24の前奏曲集』で、そこにアリス=紗良・オット自身の編曲作品を含め、リゲティやペルトなどの7曲の現代曲が散りばめられるという趣向でした。
映像は、トルコの建築家ハカン・デミレルという方が、このコンセプトのためにオリジナルにつくった映像とのことでした。
そして、予想通り、私はまず、この映像につまづいてしまいました。
映像はいかにも建築家らしく、幾何学的な図形だったり、建造物や回廊だったり、はたまた、幻想的な図書館だったりという具合で、コンサート冒頭にアリス=紗良・オット自身がマイクをにぎって解説したとおり、特にストーリー性はないものでした。
暗闇のなかで冒頭に現代曲が演奏されながらプログラムが始まって、やがてショパンの『前奏曲集』に入って行くのですが、その向こう側では、いつのまにか画面に映像が映し出されていました。
映し出される映像はさまざまでしたが、おおむね“ 白 ”を基調とした、明るい色彩のものでした。
私の耳には、どこか陰鬱で、深い悲しみや、底光りするようなほの暗い情熱が交錯して聴こえるショパンの『前奏曲集』なのに、映像を作成したトルコの人には、こういうカラッとした、地中海の白壁の街並みのように乾燥した光景が連想されてくるものなのかと、新鮮というより、戸惑ってしまいました。
目に見えない情景
これまで私は、音楽を聴いているときに、特に具体的な風景や何かを想像して聴いているつもりはなかったのですが、こうして自分の感じるものとまったく違ったものが実像として映し出されてしまうと、ここまで違和感があるものかと驚きました。
たしかユーゴスラビア出身の大指揮者ロヴロ・フォン・マタチッチだったと記憶しているのですが、あるインタビューで「わたしは指揮をしながら、目に見えない情景を見ている」というようなことを話していたのを思い出します。
「目に見えない情景」。
とても含蓄のある言葉です。
きっと私も普段、音楽を聴きながら、目には見えない情景を無意識ながらに見つめているんでしょう。
だから、その目には見えない、自分の心に映し出されている何かと、まったくちがった映像がスクリーンに映し出されてしまうと、途端に混乱してしまうわけです。
こうしてみると、通常のリサイタルでの、ただ舞台上の演奏者が目に映っているだけの光景が、いかにありがたいものかもわかりました。
それは、邪魔にならないだけではなく、とても音楽的な光景でもあって、音楽をしている人の姿というのは、きっと、それだけでとても美しく、鑑賞に堪えるものなのでしょう。
もちろん、アリス=紗良・オット自身がきっとそうであったように、あの映像に共感し、ひきつけられる人、新鮮さを感じられる人もいるはずですから、そうした人にはどんぴしゃりの映像ということになるのでしょうが、残念ながら、私はちがっていました。
音楽と音楽のこと
それならと思って、私は目を閉じて、映像を観るのをやめてみることにました。
アリス=紗良・オットのピアノだけを聴こうと思いました。
そして、今度は、音楽につまづいてしまいました。
ショパンの『前奏曲集』は全部で24曲ですが、このリサイタルではその間に現代曲が挟まります。
このことについて、アリス=紗良・オットは、コンサート前のトークで「どうして現代の演奏家があたらしく創造、ないしは作品の再定義をしてはいけないのか」と、やや憤りすら感じさせる口調でおっしゃっていました。
なるほど、そうした考え方もあるだろうと思いました。
彼女の言葉によれば、現代曲と対照させることで、ショパンとの共鳴や反響、つまりはこのコンセプトの中心にある「エコー」を聴くことができるはずだということでした。
理論としてはなるほどと感じますし、プログラミングの妙で刺激的な体験を得ることも実際にありますが、今回の試みについては、会場で実際に聴いていて、少なくとも私には、現代曲が挟み込まれるたび、とにかくショパンが途切れ、分断されてしまっているように聴こえました。

ショパンの『前奏曲集』というのは、ピアノの旧約聖書とも讃えられるバッハの『平均律クラヴィーア曲集』を指標としていて、バッハにならってすべての調性、つまり、24曲で構成された大作です。
これだけでも40分前後の演奏時間になってしまう大きな音楽であって、これを集中度を保ち、一貫した音楽として演奏すること自体がそもそも至難の業です。
ショパン自身、そのことには細心の注意を払っていたはずで、《雨だれ》が登場するタイミングといい、実に繊細に設計されている作品だと感じています。
そこへ現代曲が7曲散りばめられ、合計で65分というプログラムに拡大されていました。
65分というと、だいたいブルックナーの交響曲第7番と匹敵する長さになります。
ショパンが構築した精妙なバランスに新しい要素を加えて、しかも、それだけの長い時間にみあう緊密さを確保するのは、並大抵のことではありません。
弾き手の創造性、聴き手の創造性
『エコーズ・オブ・ライフ』=生命のこだま。
ショパンの24の前奏曲に人生をかさねて聴くということでしたが、ふと、そうしたことは、みんな普段から無意識にやっているのではないかとも思いました。
それがまた、「聴く」という行為の、一つの要素でもあるのはないでしょうか。
どなたかが、「読書というのは、つまりは、自分自身を読んでいるんだ」というようなことをおっしゃっていました。
音楽だって、きっとそうです。
私たちは、同じ場所で、同じショパンを聴いても、みんながみんな、それぞれの心と耳でもって、それぞれのちがったショパンを受け取り、聴いているものです。
アニメーション監督の宮崎駿さんが「映画というものは、たったひとつのテーマが簡単に引き出せるようではいけない」といったことを以前おっしゃっていましたが、クラシックの作品もきっと同じで、あまりに手取り足取り、こちらの想像力をコントロールされ、誘導されてしまうと、かえって「聴く側の創造性」がうばわれてしまうように感じられました。
クラシックの演奏会場で、もうずっと昔から何の変哲もなく繰り返されている、通常のコンサートというものが、結局のところ、聴衆の創造性をある程度自由にさせてくれている、もしくは、放任してくれているスタイルでもあるのではないかと、今回、はじめて気づくことになりました。

このリサイタルは、映像をつけて、さらには、曲にも変化をつけて、アリス=紗良・オットがクリエイターとして「自由」に表現したコンサートだったと思います。
会場はおおいに沸いていたので、わたし一人が例外だったのかもしれませんが、私自身は、何かとても「不自由」を感じた公演でした。
弾き手の自由と聴き手の自由、あるいは、奏者の創造性と聴衆の創造性、そうしたことを考えさせられました。
こうして文字を並べていても、演奏そのものについてほとんど触れられないのは、私が演奏に集中できなかったからです。
もうすこし自由に、アリス=紗良・オットのピアノ、ショパンの音楽、そしてリゲティやペルトの音楽を、自分なりに受けとりたかったリサイタルでした。
音源のご紹介 その1
リサイタルとまったく同じコンセプトで、CDが出ていて、すでにオンラインの配信もされています。
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
リサイタルと同様に現代曲の挟み込みが行われていますが、index上の問題なのか、私がスマートフォンのAppleMusicで再生してみたときには、ショパンはショパンでまとまって再生されました。
何かしらのミスだと思うので、そのうち修正されてしまうでしょうが、私にはこの形のほうが、ショパンにも、アリス=紗良・オットのピアノにも身を任せやすくて、ありがたいです。
はじめてのアリス=紗良・オット
さて、こうしたことを書いていると、わたしがアリス=紗良・オットを否定しているように受け取られる方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、私自身は彼女のピアノにとても強い敬意を払っています。
その敬意は10年ほど前、私がはじめてアリス=紗良・オットのピアノ・リサイタルを聴いたときから始まっています。
ここからは、そのときの思い出をつづらせてください。
そのときのリサイタルは、地方の文化会館のようなところで行われました。
私は都心での公演は都合がつかず、行ったこともない街の、名前も初めて聞くホールで行われるリサイタルへと足を運びました。
あの日、初めて降りた駅のまわりには、とにかく閑静な住宅地がひろがっていて、はたしてこういった場所で、お客さんはどれくらい集まるものなんだろうかと、すこし不安に感じました。
そして、コンサートの開場時間になって、その予想は的中しました。
今ではありえないでしょうが、当時すでにドイツ・グラモフォンという世界的レーベルと契約していたアリス=紗良・オットのリサイタルにもかかわらず、ホールはガラガラでした。
ガラガラといったら少し大袈裟かもしれませんが、6割ほどしか入っておらず、半分弱の席が空席でした。

以前、巨匠ニコラウス・アーノンクール(1929-2016)が最後の来日公演をおこなったときにも、サントリーホールが信じられないほどの空席で唖然としたことがありました。
あのときは招聘した会社がチケットの価格設定をまちがえたのだと私は思っていますが、入場してきたアルノルト・シェーンベルク合唱団の面々が空席の目立つ客席を見ておどろき、お互いに顔を見合わせ、口々に何かを言いながら、とても怪訝な表情をしていたのは今も忘れられません。
忘れられないモーツァルト
結局、あの日、リサイタル会場は空席だらけのまま開演の時刻になってしまい、舞台にアリス=紗良・オットが登場してきました。
けれども、アリス=紗良・オットはたいしたもので、表情一つ変えず、それどころか朗らかな笑顔で、客席に親しみのこもったおじぎをして、最初のプログラム、モーツァルトの変奏曲を弾きはじめました。
そして、忘れもしません。
このモーツァルトがとってもひどかったんです。
ピアノの発表会で、どこぞのお嬢様が出てきて、ただ上手におしまいまで弾きましたというような演奏で、この先まだ2時間ほどこれを聴き続けるのかと、がっかりしてしまいました。

忘れられないシューベルト
ところが、2曲目のシューベルトのソナタになったら、突然、何の前触れもなく、まったく別人のような演奏が始まりました。
第1楽章から火のような演奏ぶり。
その勢いもさることながら、弱音部がさらに印象的で、暗さなかに、あたたかなものさえ感じられて、まるでドイツの深い森を思わせるような、懐の深さがありました。
そして、演奏にどこかデモーニッシュな感覚がただよっていて、それを本人が大切にしているのもわかりました。
悪魔的な没頭、熱に浮かされたような閃き。
第1楽章がおわると、あの空席の目立つ会場から、わっと拍手が起こったほどでした。
そのあとの楽章も、彼女が興に乗ったときは聴いているこちらが夢見心地にさせられるような瞬間があって。
あれは本当に楽しいシューベルト、絶対に忘れられないシューベルト。
こうした楽興の時というのは、ごくごく限られた音楽家だけが与えてくれる体験であって、なるほど、きっとドイツ・グラモフォンのどなたかは、こうした彼女の演奏を体験して、契約せずにいられなかったんだろうなと思いました。

展覧会の絵
リサイタル後半は、ムソルグスキーの組曲『展覧会の絵』で、これもシューベルトに次いで素敵な演奏でした。
一曲一曲を丹念に描き出すというよりは、終曲の《キエフの大門》へとなだれ込んでいくような設計になっていて、楽曲を1枚の大きな絵として捉えているような演奏でした。
すごい熱量で《キエフの大門》の最後の音まで到達したときには、このガラガラのホールでそれをやり遂げた彼女の情熱、その真摯な姿勢にもすっかり感心してしまいました。
冒頭のモーツァルトと、それに続いたシューベルトとの落差。
気まぐれとも言えるような、直感的で、即興的な演奏の輝き。
あの退屈だったモーツァルトさえ、いつの間にか楽しい思い出に変わってしまったリサイタル。
それが、私が初めて彼女の実演を聴いたときの、忘れがたい、そして、とっても大切にしている思い出です。
音源のご紹介 その2
( Apple Music↑ ・ Amazon Music ・ Spotify ・ Line Music などで聴けます)
私が聴いたリサイタルとほぼ同時期に出た、曲目がほぼ同じアルバムです。
残念ながら、そして、ありがたいことに、私があの日体験したほどの閃きと輝きはここにはありません。
私にとっては、あの日、あの場所だから出会えた一回性の音楽を思い出すために聴きたくなる録音。
私にとってのアリス=紗良・オット
その後も、何度か彼女のリサイタルを聴きに行きました。
いろいろなレパートリーを体験したものの、いまだに私にとっては、彼女はあの熱に浮かされたシューベルトのピアニストであって、いつかまた、彼女が通常のリサイタル形式でシューベルト、あるいはブラームスやショパンのソナタを演奏してくれる日が来ることをずっと心待ちにしています。
そうした機会が訪れたら、私のブログのお薦めコンサートのページでも、迷わず、お薦めしていきたいと思っています。
今回の「エコーズ・オブ・ライフ」については、私は共感することも楽しむこともできなかったわけですが、それでも、こうして彼女がひとつひとつのリサイタルに問題意識をもって、ひとつの世界を形作ろうとしている姿勢には敬意を感じています。
聴衆とのコンタクト、音楽を聴き手に届けることへの強い使命感のようなものがない人には、まったく思いつきもしないようなことを考えついて、しかも、実行しているわけです。
これから先、アリス=紗良・オットが以前のような通常のリサイタル形式のコンサートもおこなってくれるのか、あるいは、さらにまた独自の路線を進んでいくのか。
彼女が今後どういう世界を展開していくにしても、そして、仮にそれが私には楽しめない世界であったとしても、どうか、神様がそのためのじゅうぶんな時間と健康を彼女にあたえてくださいますよう、心から願わずにはいられません。